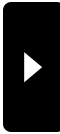冬の到来
2013年11月28日
寒くなると休憩場所は、ビニールハウス内となります。日が照るとハウス内は、30度ぐらいに温度が上昇します。
室内は、換気がないので、湿度が高いですが寒さを凌げるので助かります。今年は拡張したので広々して快適です。
寒い時は 石油ストーブを使用します。ストーブを使用する場合、室内温度が高くなるので、ポットに種をまいてもいいかなと思っています。今年はやってみようと思います。
冬場は、寒いので外での作業は、鶏の管理程度に限定されます。

侵入道路
2013年11月27日
私達が使っている道路は,通常 アスファルト舗装ですが、畑への侵入路は、土の道路で、雑草が生えます。定期的に草刈りをしないと、車が滑ってしまいます。
草刈りは、誰かが始めると順次皆さんやり始めます。道路両脇の農地の持主が、道路の半分を分担します。
この道路ですが、道なりに作ってありますから、何時も走っている道路とは感覚が異なります。慣れればどうということはないのですが、のり始めの時は、2回脱輪し、脱出するのが大変でした。
あわや、180度横転の一歩手前までということがありました。
この道も牛が通れる程度でしたが、皆さんが土地を分担して拡幅したそうです。この道がないと何もできません。
2005年7月から始めた鶏舎築造時のものです。
今となっては、懐かしい写真です。

草刈りは、誰かが始めると順次皆さんやり始めます。道路両脇の農地の持主が、道路の半分を分担します。
この道路ですが、道なりに作ってありますから、何時も走っている道路とは感覚が異なります。慣れればどうということはないのですが、のり始めの時は、2回脱輪し、脱出するのが大変でした。
あわや、180度横転の一歩手前までということがありました。
この道も牛が通れる程度でしたが、皆さんが土地を分担して拡幅したそうです。この道がないと何もできません。
2005年7月から始めた鶏舎築造時のものです。
今となっては、懐かしい写真です。
農業への思い(6)
2013年11月26日
北海道別海町の酪農研修(2週間)が終了するころ、やっと体が慣れてきたときでした。体力的にかなりハードではありましたが。
研修終了時には、俺には農業はとっても無理と確信しました。
研修終了後は、当時流行りの「カニ族」で北海道旅行をしました。宿泊は駅前。沢山の旅行者が駅前でシュラフで寝ます。旭川駅では沢山で寝る場所がなかった。
一泊目は、知床斜里駅前。ここは5人ほどでした。当時は、学生だけではなく20代の社会人も旅行していたようです。会社を辞めて自転車で北海道一周旅行している人も。
どこに行っても 学生の旅行者でいっぱいでした。学生の学割が50%でしたから。公共乗り物は、学生は50%。学生天国の時代でした。
温床の完成
研修終了時には、俺には農業はとっても無理と確信しました。
研修終了後は、当時流行りの「カニ族」で北海道旅行をしました。宿泊は駅前。沢山の旅行者が駅前でシュラフで寝ます。旭川駅では沢山で寝る場所がなかった。
一泊目は、知床斜里駅前。ここは5人ほどでした。当時は、学生だけではなく20代の社会人も旅行していたようです。会社を辞めて自転車で北海道一周旅行している人も。
どこに行っても 学生の旅行者でいっぱいでした。学生の学割が50%でしたから。公共乗り物は、学生は50%。学生天国の時代でした。
温床の完成

温床
2013年11月25日
ビニールハウス増築工事が完了し、今度は、ハウス内に温床を作り出しました。
骨組は単管で作り、稲藁を挟む骨組みは竹で拵えました。写真がその経過です。
何気ない入れ物ですが、この中に、バーク堆肥、糠、鶏糞を交互に入れて、これを3回分作って完了します。もちろん水をたっぷり入れて踏み固めます。
来年早々、この踏み固め作業をすれば、温床が稼働します。 冬の楽しみです。今年の温床は少し小さいものになりそうです。

骨組は単管で作り、稲藁を挟む骨組みは竹で拵えました。写真がその経過です。
何気ない入れ物ですが、この中に、バーク堆肥、糠、鶏糞を交互に入れて、これを3回分作って完了します。もちろん水をたっぷり入れて踏み固めます。
来年早々、この踏み固め作業をすれば、温床が稼働します。 冬の楽しみです。今年の温床は少し小さいものになりそうです。

農業への思い(5)
2013年11月23日
酪農研修で一番記憶に残っているのは、乳牛は妊娠しているから乳を搾乳できることでした。当たり前といえばそうですが。
妊娠させる場に立ち会うことが出来ました。獣医が右手に60cm以上の注射器を持ち、左の腕をカバーできる腕袋をして、牛の肛門に左腕を入れて糞を掻き出し右手の注射器を肛門に挿入し中へ精液を注入しました。
これが妊娠させる方法でした。獣医は「私によく見ておけ」と言っていました。
また、この方法でダメなときは、雄牛に交尾させるのだそうです。 鶏は交尾しなくても産卵します。
子牛は、脱脂粉乳をお湯で溶かして、哺乳瓶でミルクを与えるそうです。
九条ネギの土寄せ
妊娠させる場に立ち会うことが出来ました。獣医が右手に60cm以上の注射器を持ち、左の腕をカバーできる腕袋をして、牛の肛門に左腕を入れて糞を掻き出し右手の注射器を肛門に挿入し中へ精液を注入しました。
これが妊娠させる方法でした。獣医は「私によく見ておけ」と言っていました。
また、この方法でダメなときは、雄牛に交尾させるのだそうです。 鶏は交尾しなくても産卵します。
子牛は、脱脂粉乳をお湯で溶かして、哺乳瓶でミルクを与えるそうです。
九条ネギの土寄せ

農業への思い(4)
2013年11月22日
酪農場の朝は、早かった。朝4時から4時30分には、牛舎へ出向きます。
乳牛たちは、乳が張るので、早く搾乳して欲しくて、立ち上って べえべえ 鳴きます。
経営者は、搾乳器を乳首に装着し、搾乳します。終わると 残乳がないか確認し、残っていたら手で搾ります。乳房炎を防ぐために。
全て終わり、首輪を外してやると牧草地にいそいそ出ていきます。 寝草を搬出し、寝床を洗い、新しい寝草を敷きます。
これで朝食となります。
今日の紅葉風景
乳牛たちは、乳が張るので、早く搾乳して欲しくて、立ち上って べえべえ 鳴きます。
経営者は、搾乳器を乳首に装着し、搾乳します。終わると 残乳がないか確認し、残っていたら手で搾ります。乳房炎を防ぐために。
全て終わり、首輪を外してやると牧草地にいそいそ出ていきます。 寝草を搬出し、寝床を洗い、新しい寝草を敷きます。
これで朝食となります。
今日の紅葉風景

うこっけい
2013年11月21日
昨日 ウコッケイを購入している青梅畜産センターより、「今後宅急便による配送サービスを止める」通知文書が届きました。必要なら東京都青梅市まで引取に来ることと。
これにはビックリ。絶句でした。理由は定かではありませんが、作業が大変なのでしょう。
うううん‐‐‐。
その他の販売で購入もできますが、金額が半端ではありません。 こうなったら、種卵を買って、孵卵器で孵化させ、雛を一か月自宅で育てるしかない。
住宅地に住んでいるので、育てられるかな‐‐‐?
これから検討です。ほんまにびっくりでした。
鶏舎風景
これにはビックリ。絶句でした。理由は定かではありませんが、作業が大変なのでしょう。
うううん‐‐‐。
その他の販売で購入もできますが、金額が半端ではありません。 こうなったら、種卵を買って、孵卵器で孵化させ、雛を一か月自宅で育てるしかない。
住宅地に住んでいるので、育てられるかな‐‐‐?
これから検討です。ほんまにびっくりでした。
鶏舎風景

農業への思い(3)
2013年11月20日
今日は終日寒かった。本当に寒かった。
農業研修別海町での乳牛のお世話について。
乳牛は朝搾乳されると牛舎に併設されている牧草地に放牧されます。終日牧草地で過ごします。
夕刻になると飼い主が「べえ、べえ」と牛に呼びかけると牛舎に帰ってきますが、全てではないため、私が牛のもとへ行って追い立てます。しかし、ある牛は私に向かって突進してきますので、逃げざる負えません。境界柵を越えて逃げます。牛が行ってしますとまた追いかけます。
そんな感じで牛舎まで牛を追いかけます。
牛舎内では、牛の居場所が決まっていて、自らその場所へ行きます。首わっかを占めてやると、餌を食べ水を飲んでから寝ます。
琵琶湖バレー

農業研修別海町での乳牛のお世話について。
乳牛は朝搾乳されると牛舎に併設されている牧草地に放牧されます。終日牧草地で過ごします。
夕刻になると飼い主が「べえ、べえ」と牛に呼びかけると牛舎に帰ってきますが、全てではないため、私が牛のもとへ行って追い立てます。しかし、ある牛は私に向かって突進してきますので、逃げざる負えません。境界柵を越えて逃げます。牛が行ってしますとまた追いかけます。
そんな感じで牛舎まで牛を追いかけます。
牛舎内では、牛の居場所が決まっていて、自らその場所へ行きます。首わっかを占めてやると、餌を食べ水を飲んでから寝ます。
琵琶湖バレー

農業への思い(2)
2013年11月19日
北海道別海町への農業研修出発は全員大阪駅に集合し、急行日本海で青森、青函フエリー、札幌、別海と、若いとはいえ疲労困ぱいだった。
特に急行日本海は一日中乗っていたようで、辛かった。夜出発し、日が昇って、日が暮れてと精神的にも辛かった。半端な時間ではありませんでした。
農業研修は、酪農家が夏に牧草を刈って牧草のサイレージ(牧草の漬物)を作る作業でした。毎日広大な牧草地をチョッパーで刈って、その後ろを大型トラックが追いかけてきて刈った草をキャッチする。
結構牧草ロスもすごかったと思います。2週間毎日この作業。すべての人が農業機械を持っているわけではないので、数件の農家が機械、労働を提供しあうようです。労働力が不足していたので学生を活用したようです。結構楽しかったですが。
この研修での思い出は、次のようです。
①朝4時に起床し、牛15頭の搾汁、牛の放牧、ぼろだし、搾汁したミルク缶を冷水場所まで運ぶ。これが結構きつい。その後草刈作業へ出発。
②小学校夏休みの注意事項に、自動車の運転練習をやらない。人手が足らないので小学生にも運転させるんですね。研修中に、トラックのタイヤが溝に落ちました。私とお父さんが車の後ろでもちうあげながら小学低学年の子供が、父親の指示でアクセルとブレーキを操作していました。子供は全く前が見えません。
③お隣との距離は 400m離れており、お隣に人らしいのを見つけると大きく手を振ると向こうでも手を振っているように見える。本当にお隣との距離感が凄い。今でもその距離感を体感出来ません。
④空がめちゃ近い。星の数が半端ではない。付近に電燈がないし、全くの暗闇しかありません。感動と畏敬の念を覚えました。
⑤中間日に町主催のパーティーをがあり、牛乳や牛の足一本丸焼き肉等 が提供され圧倒されました。牛乳や肉を目いっぱい食べようと意気込んでましたが当時食べなれていないため、沢山食べられませんでした。
⑥作業中にキタキツネが突然現れたこと。
この別海町で農業を目指している人がいました。なる方法は2つ。
①跡取りのいない家に養子になること
②一生懸命農家で作業し、町役場の人に認めてもらい、多額の借金をして 農業をする。
この現実を見て、農業を行うことを断念しました。
当時は 農地を持たないものが農業をすることは、殆ど無理。
農地を借りることも殆ど不可能という時代だったと思います。

農業への思い(1)
2013年11月18日
農業への憧れは何時頃からだったかは定かではないが、中学2年生の文集で、将来農業をやっているだろうと書いていました。
父の実家が農家で水田2Ha、やぎ、午、豚等を小学校低学年頃まで飼っていたのを覚えています。やぎの乳を搾って、ご近所に配達しているのについて行った記憶もあります。
京都のゴミゴミした所が苦手だったのでしょう。高校時代にも 農業がやりたいと発言すると馬鹿にされたものでした。当然両親にも相手にされませんでした。
高校3年生の時、農業ができないか 近畿農政局まで相談に行きましたが、農地がないとどうにもならない趣旨のことを言われたのを覚えています。
致し方なく 大学受験に方向を切り替えました。一年浪人後、農学部に入学できました。大学生1年の夏休みに、北海道別海町への農業研修の募集があり、躊躇することなく 2週間の農業研修に参加しました。参加者は4名でした。
耕作地付近の紅葉

父の実家が農家で水田2Ha、やぎ、午、豚等を小学校低学年頃まで飼っていたのを覚えています。やぎの乳を搾って、ご近所に配達しているのについて行った記憶もあります。
京都のゴミゴミした所が苦手だったのでしょう。高校時代にも 農業がやりたいと発言すると馬鹿にされたものでした。当然両親にも相手にされませんでした。
高校3年生の時、農業ができないか 近畿農政局まで相談に行きましたが、農地がないとどうにもならない趣旨のことを言われたのを覚えています。
致し方なく 大学受験に方向を切り替えました。一年浪人後、農学部に入学できました。大学生1年の夏休みに、北海道別海町への農業研修の募集があり、躊躇することなく 2週間の農業研修に参加しました。参加者は4名でした。
耕作地付近の紅葉